2025年10月13日(スポーツの日)、都立小金井公園にて会員限定の第三回「華佗五禽戯」イベントを開催しました。残暑が過ぎた秋の爽やかな空気の中、長夏(ちょうか)の戯である「熊戯」の練習を通じて体を鍛えました。
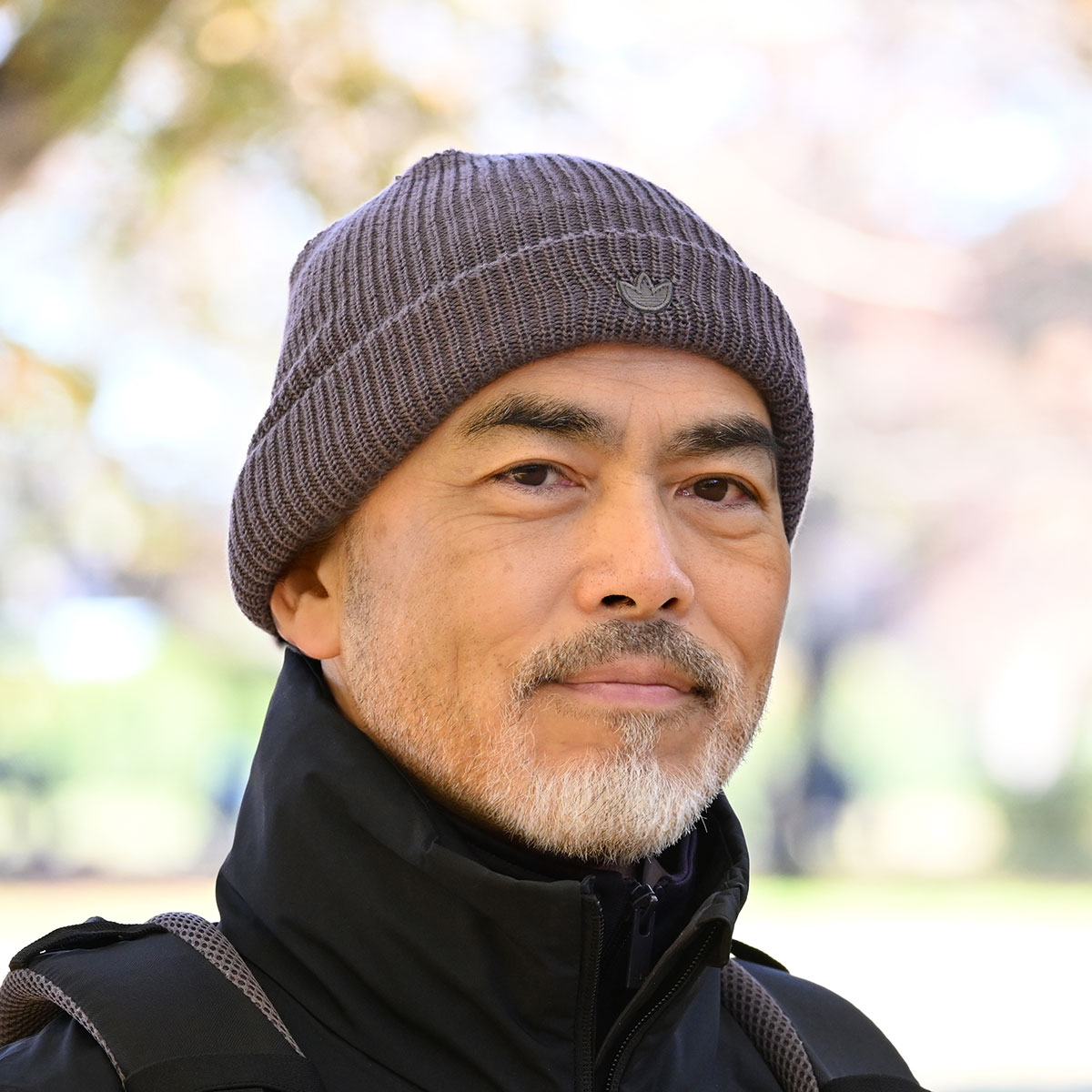 田中稜月
田中稜月この記事を書いた人
吉祥寺カンフーライフ代表/指導員
長夏(ちょうか)には脾胃の機能を高める「熊戯」



熊戯(くまのぎ)とは?
熊は脾にあたり脾胃を鍛えます。良く食べ、たくましい体を持ち、慎重で力強い熊の動きを真似することで、脾胃の働きを助け、食物の消化吸収を促し、丈夫な体格をつくり、また睡眠・精神の安定を高めることができます。
中国最古の医学書『黄帝内経』では、夏の終わりの蒸し暑く湿度の高い時期を「長夏」と記述されており、日本の梅雨と同じく湿度が高く蒸し暑い気候です。暑湿は人体の陽気を損ない、体内に余分な水分が溜まると、湿気を嫌う「脾」の機能が低下し、食欲不振や消化吸収機能の低下を引き起こし、心身の不調をもたらします。
熊戯は、長夏の時期に低下しやすい脾胃の働きを助ける、長夏の戯です。
食事の大切さを実感
華佗五禽戯では、それぞれの動物の生態を反映したストーリーがあるのですが、熊戯は「食べて鍛える」ことが強調されています。
イベントに向けて9月から熊戯を特訓していた私は、季節の変わり目に食欲が多少揺らいだものの、イベントの数日前からお米をたくさん食べるようになりました。お魚やお肉もいつもより多めに食べ、ぐっすり眠れる日が増えたおかげか、当日は早めに公園に到着し、開始前の自主練習ができるほど体力を維持できました。
平日はデスクワークが中心なのでそこまで空腹を感じないのですが、熊戯イベントの準備のための特訓をするなかで、改めて食の大切さ(そして熊戯の効果)を実感することができました。
小金井公園でリベンジ開催
長夏は中医学が発祥した黄河流域では夏の終わりにあたりますが、日本には夏前に梅雨があるため一年に長夏が2回あるとも考えられます。
前回、本格的な梅雨入り前の6月に第二回「華佗五禽戯」イベントとして「熊戯」を企画しましたが、6月にもかかわらず30度を超える日が続いたため、熱中症リスクを考慮して残念ながら開催を中止しました。
今回は本来の長夏の時期に天候に恵まれ、無事に「熊戯」を開催することができましたが、台風の影響で湿度が高く、夏と秋が混ざり合うような雰囲気でした。それでも、夏季の外出不足で鈍った身体に降り注ぐような自然のエネルギーを感じて「やっぱり小金井公園の自然は素晴らしいな」と感動しました。




いぶし銀のような熊戯
前回のイベントはゴールデンウィークの新緑の中で、草原を楽しく跳ね回る鹿戯だったので、無邪気に参加者の皆さんと楽しく練習できたのですが、熊戯はいぶし銀のような渋さがあり、全員で黙々と熊を模範した動きを繰り返し練習しました。


特に、「笨熊猛撃」(ほんゆうもうげき)や、「笨熊推掌」(ほんゆうすいしょう)という動作は、太極拳や八卦掌とはまた違ったシンプルで強い力を出す動きなので、参加者の皆さんも真剣な眼差して黙々と反復練習に取り組んでいました。
一般的な気功法のイメージとは違い、いざチャレンジしてみると意外に高度な身体能力を求められるのが華佗五禽戯の面白いところです。
熊になりきる難しさ
今回感じたのは、熊になりきる難しさでした。熊戯では考え過ぎるのが良くないとされていますが、動作の心地良さは実感できても、熊になりきることは至難の業でした。
本物の熊を見る機会がない一方で、連日の熊被害のニュースもあり、熊のイメージが混乱してしまったこともあると思いますが、私自身の体格や消化器系が弱い体質など「熊らしさがない」ことも関係しているのではないかと思います。




イベント中は参加者全員で動作を繰り返して覚えることに集中していたので、終了後は少し公園内を散策したのですが、どんぐり探しをしたり満開のコスモスや早咲きの子福桜(コブクザクラ)を眺めたりしているうちに、知らず知らず無心になれたのか気がつくと熊戯の動作を繰り返していました。
第三回「華佗五禽戯」イベントで改めて気づいたのは、華佗五禽戯のルーツは「動物の能力を学んで心身を鍛え、健康を保つ」ということです。
野生の熊が森や林を歩き回りながら季節を感じ、生き抜くために行動する、という自然の摂理は、「健やかに生きていきたい」と願う人間と同じなのだと、小金井公園の豊かな自然の中で少しだけ実感することができました。
熊になりきるのは難しいけど熊戯はじわじわ身体に効いてくる、この時期の身体は熊戯を必要としているんだなぁと感じました。
次回は、秋の戯である「鳥戯」を開催する予定です!








